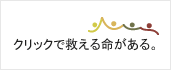Amazon strikes sweet exclusive deal – good for them, bad for consumers
そりゃすごいって最初思いましたが、独占ってのはいただけませんね。音楽もMP3という共通フォーマットを、いろんなデバイスで再生できるから便利なのであって、しかもあるアーティストが特定のプレイヤーでしか再生できないとなると、そりゃすごく不便だなって思います。e-bookリーダーも最近いろんな会社がだしてきてるし、いまでもAppleとAmazonがいるくらいだから、その一方でしか読めない本があったりすると、「KindleとiPad両方持ってないといけないのかよ」ってことにもなりかねない。まだe-book市場が定まっていないので、今はやりたい放題なのかもしれませんが、そのうち法律が制定されたりするかもしれませんね。
ゲームは昔そんな状態でしたね。ファミコンでないと、ドラクエとFFが遊べませんでした。でも、そのうちFFがプレステに移り、ドラクエも移り、といろんな紆余曲折がありましたね。最近は複数のゲームコンソールに対して同じソフトをリリースするところが多いですね。Xbox360とPS3は性能が似通っているので、ソフトも同じ物がリリースされてますね。こういう状態の方が、ユーザーとしても別のコンソールを改めて買う必要がないので、今はすごくいい状態なのかも。
e-bookは出版社(というかe-bookリーダーを作っている会社)が儲かる仕組みにするのではなく、作者が儲かるような仕組みにしてあげると、もっとたくさんの優れた作品が世にでてくるんじゃなかろうか。作家も儲かって、読者も良質な作品を手軽に読める。そんな枠組み作りは、実際は難しいかもなぁ。人の私利私欲がある限り。
<関連記事>
・ サッカーの審判はモニター見ながらジャッジすれば?
・ 3Dって必要か?
・ 便利なコーヒーチャート
<追伸>
最近暑いですね。温暖化が進んでいるのは本当なのだろうか?昔もこんな暑かったかなぁ。昔は学校にエアコンはなかったように思うが、こんな暑さをどうやってしのいでいたのだろう?まあ、単純に耐えてただけなのかもしれなくて、僕が弱くなっただけなのかもしれない。温暖化の正体は、実は人類の退化なのかも。